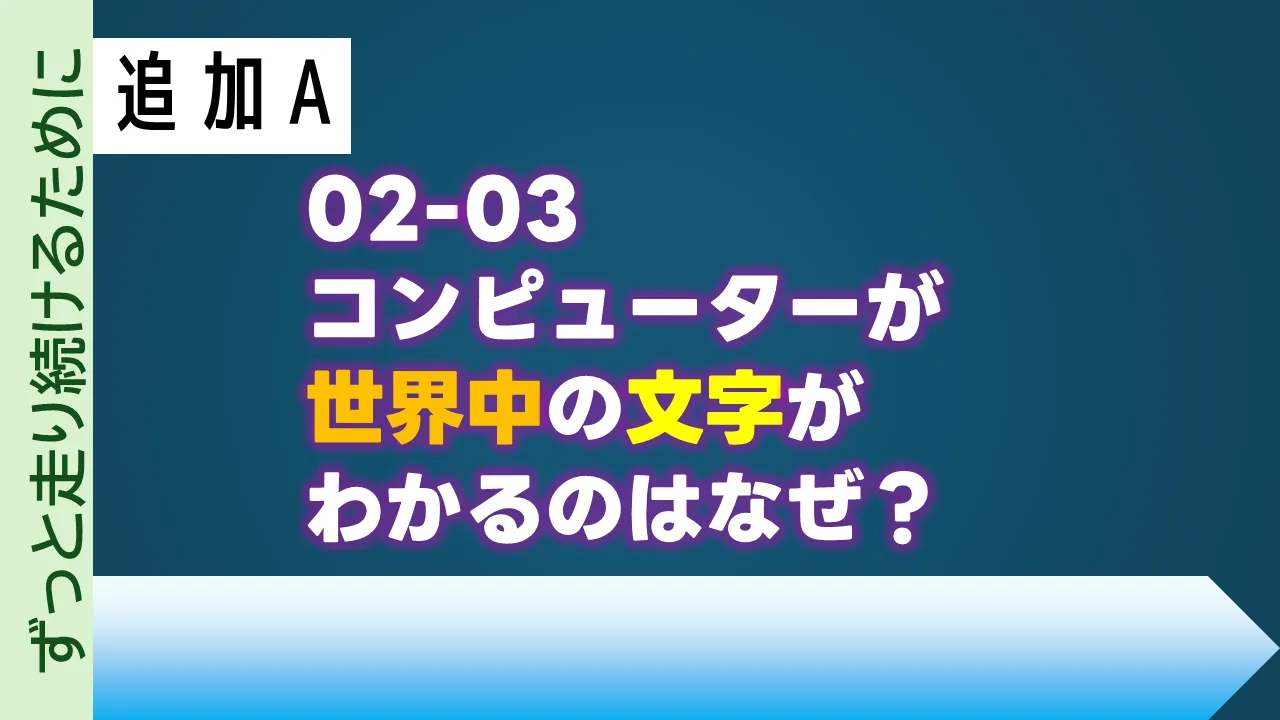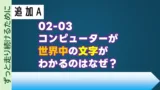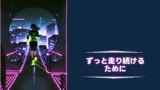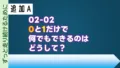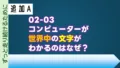聖書によれば、すべての言語の人々の中から神に選ばれた人たちだけが本物のハルマゲドンを生き残れます。その人たちは、今、聖書を正しく理解して実行していなければなりません。
聖書は、全部または一部が3000以上の言語で読めるようです。聖書を正しく教えているJW.ORGは、1080以上の言語に対応しています。
そういうことができるのは、世界中の文字がコンピューターで扱えるからです。コンピューターはどのように文字を扱っているのでしょうか。
文字に番号を付ける
コンピューターは電気信号を扱っています。8つの電気信号をひとまとまりにすると、組み合わせは全部で256通りになります。それに0から255までの番号を付けて数値にします。
コンピューターは文字をどのように理解するのでしょうか。人間のように文字を書いたり読んだりするわけではありません。
コンピューターは、文字に番号を付けています。番号を付けて管理することをコード化するといいます。文字に付けられた番号を文字コードといいます。
ワンポイント-コード化? 数値化? どっち?
物事に番号を付けることをコード化するとか、数値化するといいます。どちらもだいたい同じ意味です。
使い分けるとしたら、面積や重さなど量を扱う時は、「コード化する」ではなく、「数値化する」のほうが良いでしょう。文字に番号を付けるのは、量を扱っていませんから、「コード化する」でも「数値化する」でも、どちらも使えます。
また、コード化は数字で分類するとは限りません。緑、黄色、赤といった色や、Adder、Bison、Coyoteのような生き物などを分類名に使うこともできます。
今あなたが読んでいるこの文章も、コンピューターにとっては、文字に付けられた番号がずらっと並んでいるだけです。その番号を人間にわかる文字として、画面に描いています。
文字に番号を付けるとしても標準化されないと困る
1つ1つの文字に番号を付けるとしても、みんなが勝手に番号を付けたのでは混乱します。あるコンピューターでは[A]という文字が1番で、別のコンピューターでは[A]は100番だとしたら、コンピューター同士のやり取りは、とてもやりにくいことでしょう。
それで、アルファベットの大文字と小文字や、数字と[@]や[#]などの記号を含めて、標準化したのがASCII(アスキー:American Standard Code for Information Interchange)です。
ワンポイント-日本にはアスキーという名前の出版社と雑誌があります。
ASCIIにちなんでつけられた固有名詞ですが、ここでの説明とは直接関係はありません。
ASCIIでは、次の128種類の文字に番号がついています。
- 制御文字
- 数字と記号
- 大文字のアルファベット
- 小文字のアルファベット
制御文字とは、改行や後退など、ディスプレイやプリンターをコントロールするための信号のことです。
ASCIIは、それぞれの文字に0から127までの番号をつけました。コンピューターが1番扱いやすい単位の1バイトは、0から255までの数値を扱えるので、ASCIIはその半分なので、とても扱いやすい決まりです。ASCIIが決められたころのコンピューターのやり取りは不安定だったので、残りの128から255までの数値は、データの信頼性をチェックするのに使われました。
ほとんどのコンピューターは、ASCIIに従っています。ASCIIでは[A]という文字は65番です。65番というのは半端な数に思えますが、コンピューターにとって都合のいい数値です。このASCIIのおかげで、コンピューター同士のやり取りがとてもしやすくなります。例えば、あるコンピューターが[74,69,72,79,86,65,72]という7バイトのデータを送信したとします。どのコンピューターが受信しても[J]、[E]、[H]、[O]、[V]、[A]、[H]という文字になります。
ASCIIのおかげで、どのコンピューターでも同じように英文字を扱えるようになりました。でも、ASCIIだけだと、英語を読める人だけがJW.ORGを使えます。すべての言語の人が聖書の教えを学べるようになるために、コンピューターがどのように世界中の文字がわかるようになりましたか。次の記事で考えましょう。