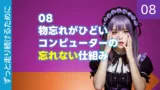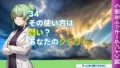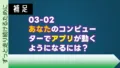アクセスという言葉は、コンピューターの話のいろいろな時に出てきます。
それだけでなく、コンピューターの話ではない時にも使われます。聖書のエフェソス2章18節にも、「have free access to the Father」と書いてあります。これは「父(神様)に自由にアクセスできる」とも訳せます。
Accessは何かに近づくイメージ
アクセス(Access)という言葉のもともとの意味は、「近づく」です。
それで、アクセスという言葉を聞いたら、まず、何かに近づくことだと思ってください。
あなたが何かに近づく時には、どうやって近づくかを考えるでしょう。そして、近づけば、さわれます。
アクセスという言葉は、何かに近づく方法や、近づいてさわることなどがイメージできます。
聖書のエフェソス2章18節は、イエス・キリストのおかげでイスラエル人でなくても神様に自由に近づけるようになったという意味です。エルサレムの神殿に行って動物の犠牲をささげなくても、神様に祈りを聞いてもらえるようになりました。
普段の時のアクセスってどういう意味?
コンピューターの話ではない時にも、アクセスという言葉を使います。どういう時ですか。
例えば、「道具はアクセスしやすいところに置く」とか、「ここの王国会館はアクセスがいい」などの言い方を聞いたかもしれません。
「道具はアクセスしやすいところに置く」は、よく使う道具は手の届く取りやすいところに置く、という意味です。道具を手の届きやすいところに置けば、気軽に使い始められるので何度も使いたくなります。
逆に、アクセスしにくいところに置くと、道具を出し入れするのが大変で、だんだんとその道具を使わなくなってしまいます。
「ここの王国会館はアクセスがいい」は、ここの王国会館は交通事情がいいので行きやすい、という意味です。きっとそこの王国会館は、道路がわかりやすいとか、電車の乗り換えを待たなくていいとか、バス停が近くにあるなどの理由で、到着するのに苦労しないのでしょう。
逆に、アクセスが悪いとは、道を間違えやすいとか、電車の乗り換えがうまくいかないとか、バス停から1時間ぐらい歩くなどの理由で、到着まで苦労するという意味です。
2つの例文で、普段の話でのアクセスという言葉がわかってきました。
「道具はアクセスしやすいところに置く」という言い方のアクセスという言葉は、道具を手の届くところに置く、という意味です。これは、手が道具と近づきやすい、とも考えられます。
「ここの王国会館はアクセスがいい」という言い方のアクセスという言葉は、王国会館までの交通事情のことです。これは、王国会館に近づく方法のこととも考えられます。
どちらも、「近づくこと」をイメージすると意味がわかってきます。
コンピューターの話でのアクセスは?
コンピューターの話でのアクセスという言葉はどういう意味でしょうか。コンピューターの話でも、アクセスは「近づく」という大きい意味は変わっていません。
ワンポイント-Microsoft Accessというアプリがある。
会社などで、たくさんのお客様情報を管理するために、データベースという種類のアプリがあります。そのデータベースアプリの1つがMicrosoft Accessです。
Microsoft Accessは、アプリの名前ですから、この記事とは直接は関係ありません。
コンピューターの動きや中身の話に出てくるアクセスという言葉の意味。
メモリやストレージを読み書きすることをアクセスといいます。
コンピューターチップは、メモリのデータを読み取って計算処理をしています。計算したものをメモリに書き出すこともあります。メモリは電気が流れている間しか記憶が残らないので、残しておきたいデータはストレージに記録します。メモリとストレージについては[08 物忘れがひどいコンピューターの忘れない仕組み]という記事があります。
ものをすぐに覚えたりメモを取るのが素早かったりする人のほうが、多くの仕事ができます。同じように、メモリやストレージもアクセスの速さが大切です。
ストレージを読み書きしている途中で、電源が切れたり、強い衝撃があったりすると、ストレージが故障します。PCはハードディスクというストレージがよく使われていました。ストレージを読み書きしている時に光るアクセスランプがあります。このアクセスランプが光っている時に、揺らしたり傾けたりするだけで故障しました。今はハードディスクの代わりにSSDが使われるようになって、揺らしたり傾けたりするだけでは故障しにくくなりました。でも、アクセスランプが光っている途中で、電源が切れたり強い衝撃があったりすると、ハードディスクよりもひどい故障を起こすことがあります。PCが動いていないように見えても、アクセスランプが光っているなら、ストレージの読み書きに集中している時です。ストレージの読み書きが落ち着くのを待ちましょう。
ストレージに記録されたファイルやフォルダーは、あなたが読み書きしてもいいものと読み書きしてはいけないものがあります。読み書きできるかどうかは、あなたにアクセス権があるかどうかで決まります。
例えば、家族と共用しているコンピューターには、あなたの文書や写真が保存されているだけでなく、家族が保存した文書や写真もあるでしょう。あなたは自分の文書や写真にはアクセス権がありますが、家族が保存した文書や写真はアクセス権がないので読み書きできません。
あなただけが使っているコンピューターでも、よくわからないまま読み書きすると壊してしまうファイルやフォルダーは、あなたにはアクセス権がないかもしれません。
コンピューターの持ち主なら、壊しても構わないので中を開けて部品を取り換えて自分の好きなようにカスタマイズしていく権利がある、と考える人もいます。メーカーが安全に使えるように設定してあるのを自分の好きなように変更したい人もいます。
中を開けたり、細かい設定をいじったりするのも、アクセスといいます。
でも、コンピューターの中にアクセスしてほしくないメーカーもあります。日本のメーカーは、少しでも中を見ようとすることも嫌がります。
最近のコンピューターは、細かいところまでアクセスできないようになっています。それは持ち主がコンピューターの中の細かいところまでアクセスする権利を制限している、と考える人もいます。
インターネットやSNSの話に出てくるアクセスという言葉の意味。
JW.ORGなどのWebサイトを見ようとすることをアクセスといいます。この言い方は、もう使っていることでしょう。
SNSで、誰かの発信を見たり、あなたが発信したりするのもアクセスです。もし、SNSへのアクセスに年齢制限がかかる法律ができたら、制限がなくなる年齢まで、あなたが発信できないのはもちろんのこと、他の人の発信を見ることもできません。
インターネットは、コンピューター同士のやり取りです。細かく考えると、コンピューター同士がやり取りすることをアクセスといいます。ですから、あなたが自分の目でWebサイトを見る前に、コンピューター同士はアクセスしています。
例えば、あなたがJW.ORGを見ようとすると、あなたのコンピューターはJW.ORGというコンピューターを探し出し、アクセスが始まります。あなたのコンピューターはJW.ORGにアクセスして記事を受信します。それを人間のためにきれいな見た目で表示します。
もともとサーバーという大きいコンピューターは、同時にたくさんのコンピューターアクセスできるようになっています。それでも考えていたよりも多くのコンピューターがアクセスしようとすると、サーバーはパンクします。
アクセスが集中してパンクする時は、サーバーのセキュリティが弱くなります。わざとアクセスを集中させて、サーバーのセキュリティを弱くする攻撃方法もあります。
まとめ-アクセスはやっぱり近づくこと
普段の話でも、コンピューターの話でも、アクセスという言葉は、「近づく」という意味です。
普段の話でのアクセスという言葉は、たいてい交通事情のことです。道がわかりやすさや、乗り換えの便利さなどです。
コンピューターの話では、コンピューターチップがしていることもあれば、コンピューター同士のつながりを意味することもあります。だいたい次の5つの場面があります。
- メモリやストレージの読み書き。
- ファイルやフォルダーの読み書き。
あなたが読み書きしていいかは、アクセス権があるかないかで決まります。 - コンピューターの中を開けることや、細かいところまで設定をいじること。
- Webサイトを見ること。
- SNSで誰かの発信を見たり自分で発信したりすること。
- コンピューター同士がやり取りすること。
どれも、近づいてさわることと関係があります。
ワンポイント-アクセシビリティってどういうこと?
アクセシビリティは、近づきやすさのことです。コンピューターの話でのアクセシビリティは、障害者が使えるように助ける仕組みのことです。
例えば、目の見えない人には、画面の文字が音声で読み上げられる仕組みがあります。見えにくい人には文字をとても大きくする仕組みがあります。
その他、キーボードが上手に押せない、マウスが使えない、耳が聞こえないなど、人によってできることとできないことがいろいろあります。そういう人たちもコンピューターを自分で扱えるように助けるのがアクセシビリティです。